![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)
![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)
これなら無理なく一週間に20時間の勉強ができます。
このペースなら全くの初心者が4ヶ月で日商簿記2級に合格できます。
「平日に2時間も勉強する時間はないぉ!?(´・ω・`)」
「せっかくの休日に5時間も勉強したくないぉ」
とお考えの皆さん。
勉強したくないってのは別として、勉強するための時間を捻出することは結構簡単です。
24時間を増やすことはできませんから、
やらなくていいことを減らして自由時間を作りましょう。
とたんに手持ち無沙汰になるのではないでしょうか。
それだけ普段からテレビに時間を割いているといえます。
テレビを見ないと不安になりますか?
2、3日続けてみてください。見なくても生活になんの支障もないことが分かります。
テレビは面白いものですが、得られる情報は微々たるものです。
しかもそれはほとんど実生活では役に立ちません(話題の材料にはなりますが)。
冷静にこれまでの人生を振り返ってみてください。
テレビを見ていて、「すごい得をした」とか「自分の能力が高まった」経験ってありますか?
残念ながら、私はありません。
テレビを全面的に否定するつもりはありませんが、得られるものは微々たるものです。
その時間を自己投資に使った方が、将来的にはいい結果を生んでくれるはずです。
会社員の方なら一番乗りして会社で勉強するのもいいでしょう。
1時間早く自宅を出れば通勤ラッシュに巻き込まれることもありません。
電車通勤なら、人の少ない車内で勉強することもできます。
また休日にも早起きして勉強すれば、午前中だけで2~3時間は勉強できます。
これならAM10:00くらいから予定を入れていても大丈夫です。
あとは夜に2時間くらい勉強すれば一日のノルマ達成です。
早起きすれば一日を有意義に過ごせます。
健康にもいいですし、おすすめ。
生活していると、10分間もしくはそれ以上の「何もしていない時間」というのが1日に何回も発生します。
例えば、通学、通勤に電車を利用している方は
少なくとも15分くらいは電車を待ったり、乗っていたりするはずです。
こういうちょっとした隙間の時間に勉強するのが、勉強時間を増やすコツです。
「たかが、15分くらいどうでもいいじゃない。電車の中では寝てたいよ」
と思われる方。
隙間時間を侮ってはいけません。
仮に一日の通勤・通学に往復で30分間の隙間時間があるとします。
これを1ヶ月積み重ねると、平日23日間/月×30分=690分=11.5時間(!)にも相当します。
11.5時間っていえば、1日の活動時間(私は14時間くらいだと考えています)に近い数字です。
つまり、毎日の通勤・通学の時間を1ヶ月集めれば、もう一日休日が増えると言えるでしょう。
この時間を勉強に当てれば、大きな効果が期待できるのは言うまでもありません。
ただ、隙間時間に文字を書くことは難しいです。
簿記の勉強であれば、テキストを読んだり、仕訳・勘定科目名の暗記などに使いましょう。
英語だったら英単語とかネイティブの音声を聞くのもありですね。
今日一日、「何もしていない時間」を意識してみてください。
どういう時に自分は「ぼ~」っとしているのか。
そういう時間を無駄なく使いましょう。
&sns();
簿記1級の勉強時間・難易度<<前へ 簿記初心者入門講座TOP 次へ>>簿記検定本試験用の勉強法
| ★簿記の教材① 「とある会社の経理さんが教える 楽しくわかる! 簿記入門」 | ||
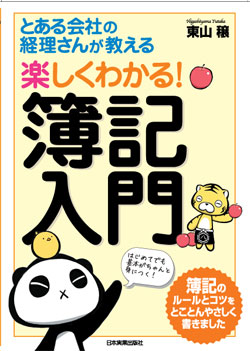 |
トコトン分かりやすく、漫画で読み進め易い簿記入門書。 恐縮ですが私の著書です。 一般的な入門書やテキストがあまり触れていない簿記の根本的な考え方に言及しています。 「なんでこんな仕訳をするの?」というところをしつこいくらい説明しています。 簿記検定の副読書としてもご活用ください。 対象は初学者、簿記3級合格者ですが、2級・1級合格者にも役立つ情報を掲載しています。 よろしければ本の中身サンプルをご覧ください。 読者様からいただいた感想もご参考ください(サイト全体に対するコメントも含まれています)。 | |
| ★簿記の教材② 「とある会社の経理さんが教える 楽しくわかる! 原価計算入門」 | ||
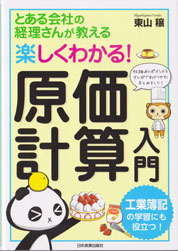 |
さらに恐縮ですが、私の著書です。私の本業、原価計算の入門書です。こちらは 日商簿記検定2級の副読書としてご活用ください。 よろしければ本の中身のサンプルをご覧ください。 日商簿記2級で登場する工業簿記に相当する範囲を収めています。 個別原価計算、総合原価計算、標準原価計算、直接原価計算を扱っています。 おサルが趣味のお菓子作りを通して 「ものを作るために要する費用」の計算方法を学んでいくストーリーです。 原価というのは材料費だけではありません。 原価計算は商売をする人にとって必修科目だと思います。 | |
| ||||||||||||
 はじめに はじめに
 仕仕紹介 仕仕紹介
|
 漫画・絵 漫画・絵
 動画 動画
 読書・書評 読書・書評
|
 学習 学習
 趣味・ビジネススキル 趣味・ビジネススキル
|
 お金を増やす お金を増やす
 その他 その他
| |||||||||