![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)
![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)
私の実体験からの考察です。
| ここでの勉強時間は日商簿記3級レベルの知識を持っている段階から始めて いくらかかるかを示しています。 ユーキャンでは1日1時間で6ヶ月と紹介しています。 6ヶ月×31日間×1時間=186時間 1ヶ月=31日で換算してちょっと割り増ししていますが、ちょっと厳しいかな?という印象。 独学で勉強するなら、個人的には220時間は欲しいところです。 LECから「20日で合格(う)かる」というキャッチフレーズの教材が市販されています。 →日商簿記検定2級用教材 簿記3級で紹介した教材の簿記2級バージョンです。 やはり20日というのはかなり厳しい数字だと思います。 ですが、これくらいの短期間で実力をつけることは可能です。 平日2時間+休日5時間で試算すると、 2時間×5日間+5時間×2日間=20時間/週 220時間÷20時間/週=11週間 |
2ヶ月と3週間あれば簿記2級合格です。
「毎日忙しいのにそんなに勉強時間とれないぉ(´・ω・`)」
という方はこちらをご覧下さい→自由時間の作り方
過去22回分の平均で算出しています。 受験率:75%(申し込みをして実際に受験する人の割合) 合格率:30.7% 合格基準:70%以上 本試験時間:2時間 受験者数:約5万人(実際に受ける人) 受験日:6月、11月、2月(年3回) 受験料:4,500円 主催:商工会議所
日商簿記2級では商業簿記と工業簿記の2科目が試験範囲です。
2時間の間に両方をこなします。
時間配分は自分で決めましょう。
おそらく時間が足りない、ということにはならないと思います。
合格率は平均して30.7%ですから決して低くはありません。
しっかり対策を立てていれば大丈夫です。
簿記2級も市販の教材での独学で十分対応できます。
3級同様書店で自分に合いそうな教材を選びましょう。
商業簿記と工業簿記にテキストと問題集が1冊ずつあるので計4冊。
4冊で総額4000円前後でしょう。
勉強法は簿記3級と同じで、各単元ごとにテキスト→問題集の流れで学習範囲が一通り終わったら、
今度は問題集だけを解いていきましょう。
分からない場合はその都度テキストで復習します。
簿記検定用の勉強方法は↓で紹介しています。参考にしてみてください。
→簿記検定本試験用の勉強法
本から本質を汲み取ることが難しいこともあります。
確実に実力をつけたいのでしたら、専門学校を利用する手もあります。
彼らは人にモノを教えるプロ集団ですから、非常にわかりやすく、
理解力の向上と勉強時間の短縮につながります。
お金との費用対効果を考え、どちらがお得なのかを考えましょう。
実際、簿記2級に合格した後に、専門学校で1級の勉強を始めてみて
2級の範囲の知識が曖昧だったことが判明しました。 独学の怖いところではあります。
強制されないと動けない人は専門学校の方がいいかもしれません。
管理人TOKEIのおすすめ教材→日商簿記検定2級用教材
管理人TOKEIのおすすめ学校→簿記検定を学べる専門学校
&sns();
簿記3級の勉強時間・難易度<<前へ 簿記初心者入門講座TOP 次へ>>簿記1級の勉強時間・難易度
| ★簿記の教材① 「とある会社の経理さんが教える 楽しくわかる! 簿記入門」 | ||
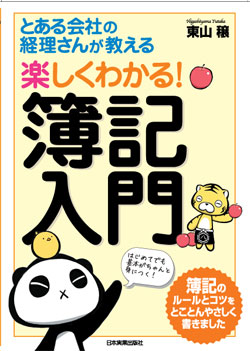 |
トコトン分かりやすく、漫画で読み進め易い簿記入門書。 恐縮ですが私の著書です。 一般的な入門書やテキストがあまり触れていない簿記の根本的な考え方に言及しています。 「なんでこんな仕訳をするの?」というところをしつこいくらい説明しています。 簿記検定の副読書としてもご活用ください。 対象は初学者、簿記3級合格者ですが、2級・1級合格者にも役立つ情報を掲載しています。 よろしければ本の中身サンプルをご覧ください。 読者様からいただいた感想もご参考ください(サイト全体に対するコメントも含まれています)。 | |
| ★簿記の教材② 「とある会社の経理さんが教える 楽しくわかる! 原価計算入門」 | ||
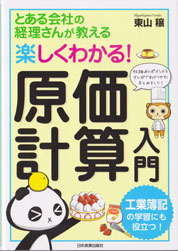 |
さらに恐縮ですが、私の著書です。私の本業、原価計算の入門書です。こちらは 日商簿記検定2級の副読書としてご活用ください。 よろしければ本の中身のサンプルをご覧ください。 日商簿記2級で登場する工業簿記に相当する範囲を収めています。 個別原価計算、総合原価計算、標準原価計算、直接原価計算を扱っています。 おサルが趣味のお菓子作りを通して 「ものを作るために要する費用」の計算方法を学んでいくストーリーです。 原価というのは材料費だけではありません。 原価計算は商売をする人にとって必修科目だと思います。 | |
| ||||||||||||
 はじめに はじめに
 仕仕紹介 仕仕紹介
|
 漫画・絵 漫画・絵
 動画 動画
 読書・書評 読書・書評
|
 学習 学習
 趣味・ビジネススキル 趣味・ビジネススキル
|
 お金を増やす お金を増やす
 その他 その他
| |||||||||